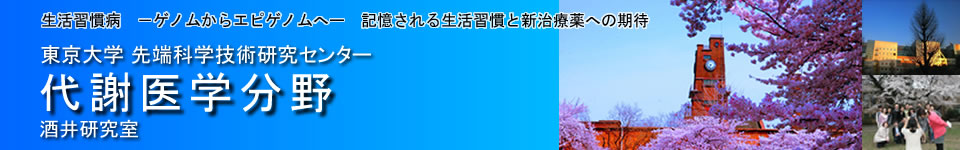脂肪を燃えやすくする酵素を特定、Nat Communに掲載。Histone demethylase JMJD1A coordinates acute and chronic adaptation to cold stress via thermogenic phospho-switch.
Abe Y, Fujiwara Y, Takahashi H, Matsumura Y, Sawada T, Jiang S, Nakaki R, Uchida A, Nagao N, Naito M, Kajimura S, Kimura H, Osborne TF, Aburatani H, Kodama T, Inagaki T, Sakai J* (* corresponding authors).
Histone demethylase JMJD1A coordinates acute and chronic adaptation to cold stress via thermogenic phospho-switch.
Nat Commun, 9, 1566, 2018. [DOI] [PubMed] [Journal Web Site]
◆持続的な寒さに対し、体には脂肪を燃焼し、熱を産生し、体温を維持するしくみが備わっています。
◆持続的な寒さによって生じる白色脂肪細胞のベージュ脂肪細胞(注1)への変化の過程にて生じるヒストンの持つ脱メチル化酵素のリン酸化が、エピゲノム(注2)の変化において、重要な役割を持っていることがわかりました。
◆本成果は、肥満や生活習慣病に対する新たな治療法や予防法への応用が期待されます。
発表概要:
恒温動物は寒冷環境に適応するしくみを持っていますが、この際に重要な役割を持つのが脂肪細胞です。急激に環境の温度が低下すると交感神経系が活性化し、褐色脂肪細胞(注3)で脂肪が燃焼され、熱が産生されます。一般によく知られている白色脂肪組織は、エネルギーを脂肪として貯めることが主たる役割であるため熱産生能を有しておらず、熱産生に関与する遺伝子(注4)も発現していません。しかし、寒冷環境が長期に持続すると、白色脂肪組織でも、脂肪燃焼と熱産生に関わる遺伝子が誘導され、寒冷環境に個体が耐えられるよう適応します。
本来、細胞には「エピゲノム」というゲノムの後天的な調節機構が備わっており、エピゲノムのしくみにより細胞の種類ごとに働く遺伝子(活動中)と働かない遺伝子(休止中)が明確に決められています。脂肪を貯める機能を担う白色脂肪細胞では、通常は脂肪燃焼や熱産生に関わる遺伝子は「休止中」で、働くことができません。では、恒温動物が長期の寒冷刺激を受けると、どのようにして遺伝子に寒冷環境に適応した体質への変化を促すのでしょうか?
東京大学先端科学技術研究センター/東北大学 大学院医学系研究科の酒井寿郎 教授、群馬大学生体調節研究所の稲垣 毅 教授、学術振興会特別研究員の阿部陽平、東京大学大学院薬学系研究科大学院生の藤原庸右および東京大学大学院医学系研究科大学院生の高橋宙大らの研究グループは、遺伝子がエピゲノムによって通常は「休止中」となっている白色脂肪組織に着目し、慢性の寒冷刺激による脂肪組織のベージュ化過程におけるエピゲノム解析を行いました。寒冷刺激を受けるとアドレナリン作用によってヒストン脱メチル化酵素JMJD1A(注5)がリン酸化され、寒冷刺激が持続すると必要な機能を獲得したJMJD1A がエピゲノム変化を介して「休止中」だった脂肪燃焼と熱産生に関わる遺伝子群を「活動中」にし、遺伝子を発現させて、ベージュ化を誘導し、寒冷環境に慢性的に適応するしくみがあることがわかりました(図)。本成果は、肥満や生活習慣病に対する新規治療法の開発に応用できるものと期待されます。
本研究は、文部科学省 科学研究費 基盤研究(S)「環境因子とエピゲノム記憶による生活習慣病発症の解明」、新学術領域研究「温度生物学」、文部科学省の産学連携プログラムである先端融合領域イノベーション創出拠点の形成プログラム「システム疾患生命科学による先端医療技術開発」等の支援のもとで行われたものです。本研究成果は国際科学誌 Nature Communications に2018年4月19日付オンライン版で発表されました。
発表内容:
<研究の背景>
寒さは命に関わる低体温症を引き起こすおそれのある危険な環境です。恒温動物は寒さに応答し、適応するために、脂肪を燃焼し熱を産生するシステムを持っています。私たちの身体には、皮下の白色脂肪組織に存在し、エネルギーを脂肪として貯める白色脂肪細胞と、褐色脂肪組織に存在し、脂肪を燃焼し熱を産生する褐色脂肪細胞があります。白色脂肪細胞も褐色脂肪細胞も生まれながらに備わっています。恒常的に存在する褐色脂肪細胞は、個体への寒冷刺激にともなって短時間で急激に脂肪燃焼や熱産生に関わる遺伝子の発現を増加させ、熱産生の容量を最大限に増大させます(図上)。これに加えて、「ベージュ脂肪細胞」とよばれる第二の熱産生脂肪細胞の存在が近年明らかにされています。褐色脂肪細胞が特に新生児に多く存在するのに比べ、ベージュ脂肪細胞は寒さに適応していくために新たにつくられる「誘導型」の熱産生脂肪細胞です。
後天的なゲノム修飾であるエピゲノムは、ゲノムの遺伝情報のうち、実際に働く領域(活動中)と働かない領域(休止中)を決定し、細胞の記憶として機能します。褐色脂肪細胞では、脂肪燃焼や熱産生に関わる遺伝子はエピゲノムの働きによって「活動中」のクロマチン構造(注6)をとっています。一方で、脂肪を貯めることが主たる役割である白色脂肪組織では、脂肪燃焼や熱産生に関わる遺伝子は「休止中」のクロマチン構造をとっているため、寒さの刺激ですぐに脂肪燃焼や熱産生に関わる遺伝子の発現が誘導されることはありません。
<研究の内容:>
研究グループは、先行研究で短期の寒冷刺激に伴いJMJD1A の 265 番目のセリン残基がリン酸化され、急性期の熱産生に必要な機能を獲得することを見出しました(Nature Communications 2015)。今回、265 番目のセリン残基をリン酸化されないアラニン残基に置換した変異型 JMJD1A をもつマウスを作製し、寒さに対する適応を解析しました。急激な寒冷刺激下では、変異体マウスは寒冷を感知できないため、通常のマウスと比べて顕著に体温が低下しました。また長期(一週間)の寒冷刺激下では、変異体マウスは寒冷刺激をエピゲノムに伝えることができないため、野生型マウスと比較して、脂肪燃焼、熱産生、そして白色脂肪組織のベージュ化が顕著に抑制され、寒冷への適応力が低下していることが明らかになりました。
ベージュ脂肪細胞は、熱産生のために糖や脂肪を活発に消費します。白色脂肪組織のベージュ化が抑制されている変異体マウスは、高栄養の食事を与えると野生型(通常の)マウスと比べ、インスリンのはたらきが悪く、高インスリン血症を呈しました。この研究の結果は、インスリンのはたらきが悪くなる2型糖尿病の治療法に応用できると考えています。
今回の研究から、寒冷環境への適応のしくみについて、(1)恒温動物が寒さに直面すると、褐色脂肪組織のJMJD1Aが寒さを感知することで急速な熱産生を行い、(2)寒さが長期に持続すると白色脂肪組織のJMJD1Aが寒さをエピゲノムに伝え、脂肪を燃焼し熱を産生する「誘導型」のベージュ脂肪細胞を新たにつくる、ということがわかりました。また、白色脂肪組織のベージュ化では、寒さの感知によるJMJD1Aのリン酸化(第一段階)、ヒストン脱メチル化によるエピゲノムの変化(第二段階)、という機構を介して、「休止中」の脂肪燃焼と熱産生に関わる遺伝子を「活動中」にし、慢性的な寒さに適応することが初めて明らかとなりました。
<社会的意義>
ベージュ脂肪細胞は、熱産生のために糖や脂肪を活発に消費することから、近年、栄養過多に伴う2型糖尿病などの生活習慣病の治療標的として注目されています。JMJD1A のリン酸化を標的とした脂肪組織のベージュ化機構にもとづく生活習慣病の治療・予防法の開発に応用できるものと期待されます。
A new study in fat cells has revealed a molecular mechanism that controls how lifestyle choices and the external environment affect gene expression. This mechanism includes potential targets for next-generation drug discovery efforts to treat metabolic diseases including diabetes and obesity.
Researchers tracked how the epigenome changes after long-term exposure to cold temperatures, and how those changes cause energy-storing white fat cells to become heat-producing brown-like, or "beige," fat cells.
"We believe that this is the first time that anyone has collected data to prove that there are two steps between the environmental stimuli and epigenetic changes," said Professor Juro Sakai from the University of Tokyo and Tohoku University, an expert in the epigenetics of metabolism.
Gene expression is regulated by epigenetics - patterns of chemical signals that are "above" the gene sequence. An individual's gene sequence is determined at conception, but the external environment and an individual’s lifestyle can change the epigenetic sequence throughout a lifetime, continually altering how genes are expressed. The scientific community has long suspected that there may be a stepwise process inside the cell to manage environmental influences on the epigenome, but no specific molecular mechanisms had been identified previously.
Shivering creates body heat short-term by warming up the muscles, but thermogenesis is the chemical process by which brown fat cells can use lipids (fat) to create heat to keep the body warm long-term. Brown fat is regarded as healthier and is not associated with the metabolic diseases linked to excess white fat.
When organisms are cold for a long time , the sympathetic nervous system responds by releasing adrenaline. If cold temperatures persist, those adrenaline signals eventually reach white fat cells. Step one of the environmental epigenetic control pathway is that the cell initiates a specific change to one amino acid in a protein named JMJD1A and this altered JMJD1A recruits other proteins. In step two, this JMJD1A protein complex is recruited to genes that initiates thermogenesis and changes their epigenetic pattern so that they are active. Those epigenetic changes transform white fat cells into what researchers refer to as "beige fat cells," which perform thermogenesis like brown fat cells.
More beige fat cells and fewer white fat cells could reduce the symptoms or negative health outcomes of metabolic diseases like diabetes, obesity. Although transforming white fat cells into beige fat cells and increasing thermogenesis is naturally a stress response to chronic cold exposure involving adrenaline, researchers report that the same white-to-beige fat cell transition can be caused without adrenaline or cold stress.
"Understanding how the environment influences metabolism is scientifically, pharmacologically, and medically interesting. Our next experiments will look more closely at epigenetic modifications within the thermogenesis signaling pathway so that we may manipulate it," said Sakai.
Current drugs for metabolic diseases rely on hormones that are systemic throughout the entire body or drugs that target entire proteins. Sakai's research team imagines a future where metabolic diseases can be treated by targeting single amino acids.
The JMJD1A protein is involved in a wide variety of other processes, including cancer, infertility, stem cell renewal, and sex determination of an embryo. However, Sakai's research team has discovered sites within the protein sequence that are extremely specific for controlling different activities of the protein. Manipulating those specific amino acids may provide precision drug targets.
The published study included research using mice and mouse cells. Chronic cold exposure in humans can include living in places that are often below 4oC (39.2oF). In addition to living in cold environments, brown fat thermogenesis is essential for newborn infants anywhere in the world as they acclimatize from the 37oC (98.6oF) temperature in the uterus to common room temperature of approximately 23oC (73.4oF).
Press release (Japanese)
Paper
, "Histone demethylase JMJD1A coordinates acute and chronic adaptation to cold stress via thermogenic phospho-switch", Nature Communications Online Edition: 2018/04/19 (Japan time), doi: 10.1038/s41467-018-03868-8.
Article link (Publication)
Links
Research Center for Advanced Science and Technology
転写因子SREBPの活性化機構を解明
Sakai J, Duncan EA, Rawson RB, Hua X, Brown MS, and Goldstein JL Sterol-regulated release of SREBP-2 from cell membranes requires two sequential cleavages, one within a transmembrane segment. Cell, 85, 1037-1046. (1996)
この論文ではコレステロールによる遺伝子発現を制御する転写因子 sterol regulatory element binding protein(SREBP)の活性化機構を明らかにした。
膜結合型のSREBPが初めは小胞体膜上にヘアピンループ構造をとって存在し、 コレステロールが欠乏すると2つの蛋白分解酵素による連続した切断を受け NH2末端の成熟型SREBPが核に移動し、 コレステロール代謝を制御する遺伝子群を活性化することを明らかにした。 論文は膜結合蛋白のプロテアーゼによる切断が転写を調節する機構の解明として生命科学に大きく貢献した。
SREBP切断酵素 Site-1プロテアーゼ(S1P)の同定
Sakai J, Rawson RB, Espenshade PJ, Cheng D, Seegmiller AC, Goldstein JL, and Brown MS Molecular identification of the sterol-regulated luminal protease that cleaves SREBPs and controls lipid composition of animal cells. Molecular Cell, 2, 505-514. (1998)
上記の研究をさらに進め、SREBPが切断されると分泌型アルカリフォスファターゼが 培地中に分泌するアッセイ系を作成し、プロテアーゼ欠損のCHO細胞株から、ステロール応答性にSREBPを 切断するプロテアーゼの遺伝子を発現クローニングした。
このプロテアーゼはセリンプロテアーゼのスーパーファミリーに属して、 SREBPの「コレステロール応答性二段階SREBP切断機構」の第一回目のサイトを切断することから Site-1プロテアーゼ(S1P)と命名された。
酢酸を活性化する酵素(アセチルCoA合成酵素)欠損マウスは絶食時に体温、持久力が低下する。
―酢酸が絶食時の燃料になることを発見―
Sakakibara I, Fujino T, Ishii M, Tanaka T, Shimosawa T, Miura S, Zhang W, Tokutake Y, Yamamoto J, Awano M, Iwasaki S, Motoike T, Okamura M, Inagaki T, Kita K, Ezaki O, Naito M, Kuwaki T, Chohnan S, Yamamoto TT, Hammer RE, Kodama T, Yanagisawa M, Sakai J. (2009) Fasting-induced hypothermia and reduced energy production in mice lacking acetyl-CoA synthetase 2. Cell Metabolism, 9, 191-202.
我々は日常の調理で酢を使いますが、体内(肝臓)でも合成、血中に放出されています。これまで脂肪酸やケトン体が、絶食・飢餓といった食事を摂れない状態、あるいはインスリンの利用が極端に減少した糖尿病状態では、ブドウ糖に代わり、エネルギーとして利用されることが生化学・内科学の教科書的知識として知られていました。
今般の発見は日常的に用いられる酢酸が、ブドウ糖の吸収・利用が極端に低下した状態で、最終的なエネルギー源として必須であることを示した基本となる事例です。 Acetyl-CoA synthetase 2 (AceCS2)は酢酸をアセチル-CoAという物質に活性化する酵素です。クエン酸回路ではこのアセチル-CoAがATP(アデノシン3リン酸)や電子伝達系で用いられるNADHなどを生じ、効率の良いエネルギー産生を可能としております。AceCS2を欠損した動物では絶食時に、このATPやNADHが欠乏し、燃料不足から低体温や持久運動の低下を来します。
こと、生後間もない授乳期には(糖分が少ないなど母親のミルクの成分に起因すると考えられますが)、酢酸の利用はことのほか重要で、AceCS2を欠損し、酢酸を利用できない動物は授乳期には成長に障害を来します。離乳後、通常の食事を摂るようになると成長は元に戻ります。しかし離乳後もブドウ糖の少ない食事をあたえると、酢酸を利用できない動物の場合、50%が低体温、低血糖となり死亡してしまいます。
一方、現代の飽食時代にあっては、肥満・メタボリック症候群が社会的にも問題になっています。米国では近年、低インスリンダイエット(低炭水化物ダイエット、いわゆるアトキンズダイエット)が、低脂肪食にかわる効果的ダイエットとしてブームになっています。
今回の、酢酸を活性化する酵素を欠損したマウスでは、低インスリンダイエットによって体重増加がさらに抑えられることも明らかとなり、このダイエット法においては酢酸を活性化する阻害剤が、今後、抗肥満薬として効果を上げる可能性が示唆されました。
寒冷刺激時の体温維持には熱産生遺伝子の高次構造変化が必須
~寒冷の感知によるJMJD1Aタンパク質のリン酸化と遺伝子DNAの高次構造変化~
私たちヒトや哺乳動物は、急激な環境の変化に瞬時に反応し、生命を守るしくみがあります。例えば、からだが寒冷環境という低体温が引き起こされうる危険な状態にさらされると、中枢でこれを感知し、交感神経からの刺激によって、熱産生を専門に行う褐色脂肪組織(注2)で迅速に熱が産生され、低体温になることを防ぎます。これまで、核内でDNAが巻き付くヒストンタンパク質のメチル基を除く働きのあるJMJD1Aタンパク質(注3)を欠損したマウスは低体温に陥ることがわかっていましたが、そのしくみの詳細は明らかではありませんでした。
東京大学先端科学技術研究センター 代謝医学分野の酒井 寿郎 教授、稲垣 毅 特任准教授、阿部 陽平 特任研究員、Royhan Rozqie (東大 先端研 大学院生)らの研究グループは、寒冷時に熱産生遺伝子の発現を急速に活性化して体温を維持するには、従来知られていた「転写因子」と呼ばれるタンパク質群の働きだけではなく、熱産生をつかさどる遺伝子DNAの急速な高次構造変化が必須であることを解明しました。
交感神経から寒冷刺激を受けたJMJD1Aタンパク質はリン酸化され、これが引き金となって、「遺伝子の高次構造を変化させる複数のタンパク質群 (SWI/SNF complex)」が熱産生遺伝子に結合し、遺伝子の発現を活性化させることがわかりました。これら一連の変化は十数分の速さでおこり、熱産生に関わる遺伝子の発現を急速に促します。
本成果は、JMJD1Aタンパク質を標的とした低体温症や肥満への新規治療法や予防法にもつながると期待されます。
本研究成果は国際科学誌Nature Communicationsに2015年5月7日付オンライン版で発表されました。
JMJD1A is a signal-sensing scaffold that regulates acute chromatin dynamics via SWI/SNF association for thermogenesis
Yohei Abe 1, Royhan Rozqie 1, Yoshihiro Matsumura, Takeshi Kawamura, Ryo Nakaki, Yuya Tsurutani, Kyoko Tanimura-Inagaki, Akira Shiono, Kenta Magoori, Kanako Nakamura, Shotaro Ogi, Shingo Kajimura, Hiroshi Kimura, Toshiya Tanaka, Kiyoko Fukami, Timothy F. Osborne, Tatsuhiko Kodama, Hiroyuki Aburatani, Takeshi Inagaki*, Juro Sakai*. Nature Communications online edition, 6:7052, 2015, DOI:10.1038/ncomms8052
研究成果解説
私たちヒトや哺乳動物は、急激な環境の変化に瞬時に応答し生命を守るしくみがあります。例えば、からだが寒冷という危険な状態にさらされると、中枢でこれを感知し、交感神経からはノルアドレナリンというホルモンが分泌されて、熱産生を専門に行う褐色脂肪組織ですみやかに熱が産生され、低体温になることを防ぎます。急速に外界の温度が低下したとき、これを感知し、交感神経の活性化から熱を産するためには数分の速さで対応できるしくみが必要です。これまで、研究グループは、DNAが巻き付いているヒストンタンパク質のメチル基を除く働きのあるJMJD1Aタンパク質を欠損したマウスは低体温に陥ることを突き止めていましたが(図1)、そのしくみの詳細は明らかではありませんでした。
今回、研究グループは、JMJD1Aという核内タンパク質が寒冷刺激にともない交感神経刺激を介してリン酸化されることで、「遺伝子の高次構造を変化させる複数のタンパク質群」が熱産生遺伝子DNAに結合し、「長距離DNAルーピング」と呼ばれる遺伝子DNAの高次構造変化を起こすことによって、熱産生遺伝子の発現を活性化させることを明らかにしました。これら一連の変化は数分の速さでおこり、熱産生に関わる遺伝子の発現を急速に活性化することを明らかにしました。
研究グループは、質量分析解析から交感神経刺激によって核内のJMJD1Aの265番目のセリン残基がリン酸化されることを見出しました(図2)。このアミノ酸をアラニンに置換しリン酸化されない変異体JMJD1Aを褐色脂肪細胞に発現させると、寒冷刺激で誘導される熱産生遺伝子群の発現誘導が著しく低下し、実際に、褐色脂肪細胞での熱産生が低下しました。さらに質量分析解析から、このJMJD1Aがリン酸化されることが引き金となり「遺伝子の高次構造を変化させる複数のタンパク質群(SWI/SNF、注4)」や「褐色脂肪細胞の機能に重要な核内受容体 (PPARg、注5)」と集合体を形成することを見いだしました(図3)。この複合体にある核内受容体が熱産生応答に必要な遺伝子を選び出し、それらの遺伝子上の遠隔にある遺伝子発現活性化領域を、「DNAルーピング」と呼ばれる遺伝子の高次構造変化を介して引き寄せ遺伝子発現を活性化することを明らかにしました(図3)。
このJMJD1Aのリン酸化は、交感神経からの刺激があってから数分で認められ、これと同期して遺伝子の高次構造が変化し、さらに熱産生遺伝子の発現が促進されました。DNAが巻き付くヒストンタンパク質の脱メチル化酵素として発見されたJMJD1Aは、リン酸化で誘導されるタンパク質複合体・動的な遺伝子立体構造変化によって転写を促進させ、熱産生・エネルギー消費を制御するという、数分の速さでの急性応答に関与するという従来知られていなかった別の機能をもっていることがわかりました。また、本研究は多様な機能を持っているJMJD1Aタンパク質が、ある特定の環境からの刺激によって、応答に必要な特定の遺伝子をどのようにして選び出して発現を調節し、環境へ適応・応答するのかを明らかにしたものです。
以上のように、寒冷刺激に応答し、核内で遺伝子DNAがダイナミックに構造を変化させ、迅速に熱を産生するしくみを明らかにしました。このしくみには、JMJD1Aタンパク質が寒冷刺激を感知して265番目のセリン残基がリン酸化されることが鍵となることがわかりました。今後、このアミノ酸のリン酸化を制御するタンパク質を明らかにし、低体温の治療、あるいは、熱産生・エネルギー消費が低下して起こる肥満症への治療法につながると期待されます。
発表のポイント:
- 私たちの体には、寒さに反応してすみやかに熱を産生して体温を維持するしくみがあります。
- 寒冷時に体温を維持するには、転写因子と呼ばれるタンパク質群の働きだけではなく、熱産生に関与する遺伝子(注1)の急速な立体構造の変化が必須であることを解明しました。
- 本成果は、低体温症や熱産生低下に伴う肥満への新規治療法や予防法につながると期待されます。
用語解説
(注1)熱産生に関与する遺伝子:交感神経から分泌されるノルアドレナリンなどの受容体であるβアドレナリン受容体 (b-AR)や、ミトコンドリアにある脱共役タンパク質など、熱を産生するために必要な鍵となるタンパク質群をコードする遺伝子群をさす。b-ARは交感神経から分泌されるホルモンである ノルアドレナリンに結合し、交感神経刺激を褐色脂肪細胞に伝達する最初のステップをつかさどり、Ucp1はミトコンドリア内膜に局在し、酸化的リン酸化のエネルギーをATPの代わりに熱として生成する最終ステップをつかさどる。
(注2)褐色脂肪組織または褐色脂肪細胞:哺乳類に存在する脂肪組織または脂肪細胞の1つ。もう一つのタイプの白色脂肪組織または白色脂肪細胞が主として脂肪を貯めるのに対し、褐色脂肪組織の主な機能は体を震わせないでからだの熱を産生すること。ノルアドレナリンが褐色脂肪細胞上のβアドレナリン受容体に結合すると、脱共役タンパク質UCP1が生成され、ミトコンドリアで脱共役が起こり、ATPの代わりに熱が産生される。
(注3)JMJD1A:ヒストン脱メチル化酵素。体重の制御、性決定、がん発生、低酸素による応答など、環境応答に多様に機能する。本研究グループは、JMJD1Aという脱メチル化酵素が欠損したマウスが寒冷時に低体温になり、肥満を呈することから、エネルギー消費・熱産生の制御に深く関わっていることをこれまで明らかにしてきた。
(注4)SWI/SNF複合体:ヌクレオソームと呼ばれるDNAがヒストンというタンパク質に巻き付いている構造を開いて遺伝子の発現を促進させるタンパク質群。
(注5)PPARg (peroxisome proliferator-activated receptor g):核内受容体の一つ。脂肪細胞分化・機能維持の中心となる分子。この合成アゴニストはインスリン抵抗性改善薬として広く糖尿病の治療薬として使われている。

図1:寒冷刺激によるマウスの体温の変化。
JMJD1Aを欠損したマウスは寒冷環境ではJMJD1Aを欠損していない野生型動物と比べ体温が低下する。

図2:褐色脂肪細胞における寒冷刺激による急速な熱産生遺伝子誘導のしくみ
環境温度の低下を脳が感知すると、交感神経が活性化され、ノルアドレナリンが神経終末から分泌される。ノルアドレナリンは、褐色脂肪細胞上のbアドレナリン受容体に結合し、細胞内シグナリングを経て、タンパク質リン酸化酵素 (PKA) を活性化する。活性化されたリン酸化酵素PKAは核内のJMJD1Aタンパク質を265番目のセリンでリン酸化する。このリン酸化が引き金となり、「遺伝子の高次構造を変化させる複数のタンパク質群」が熱産生遺伝子DNAに結合し、遺伝子DNAの高次構造変化を起こし、遺伝子発現を上昇させる。これら一連の変化は数分から十数分の速さでおこる。熱を作り出す脱共役タンパク質(Ucp1)や b アドレナリン受容体(bAR)などの熱産生関連の遺伝子発現を急速に増加させ、熱産生に寄与する。
(略語 β-AR: β-アドレナリン 受容体、UCP1: 脱共役タンパク質、cAMP: β-AR シグナルの2ndメッセンジャー、PKA: タンパク質リン酸化酵素)

図3:遺伝子の急速な立体構造変化
従来知られている転写因子を介する制御とともに、寒冷刺激によりJMJD1Aがリン酸化されると、遺伝子高次構造を変化させるタンパク質複合体(SWI/SNF)と核内受容体 PPARgタンパク質複合体をつくり、長距離DNAルーピング」と呼ばれる遺伝子DNAの高次構造変化を急速に変化させることで、熱産生・エネルギー消費を制御していることを解明した。
Wntシグナルの受容体LRP5を欠損させたマウスでは骨密度の低下とともにインスリン分泌不全による糖代謝異常を引き起こす。
-老化における代謝変化を調節するWnt系の役割-
Fujino T, Asaba H, Kang MJ, Ikeda Y, Sone H, Takada S, Kim DH, Ioka RX, Ono M, Tomoyori H, Okubo M, Murase T, Kamataki A, Yamamoto J, Magoori K, Takahashi S, Miyamoto Y, Oishi H, Nose M, Okazaki M, Usui S, Imaizumi K, Yanagisawa M, Sakai J *(corresponding author), Yamamoto TT. (2003) Low-density lipoprotein receptor-related protein 5 (LRP5) is essential for normal cholesterol metabolism and glucose-induced insulin secretion. Proc Natl Acad Sci U S A, 100, 229-234.
従来の老化関連疾患研究では、加齢に伴う基礎代謝の低下、骨密度低下、栄養過剰への適応力の低下などが指摘されている。しかし個々の現象を制御し、加齢に伴う代謝変化を決定している基本的調節系は不明です。
私たちはWnt蛋白やWnt受容体の発現量をはじめとするWnt系のシグナルが代謝活性を調節する可能性を発見しました。私たちはWnt受容体(LRP5)欠損マウスの作製・解析から、Wntシグナルが低下し、インスリン分泌不全、易動脈硬化、食後の高脂血症、骨密度低下などの生活習慣病・老化ともいった症状が加齢とともに一層発症しやすくなることを示しました。このマウスでは核内受容体、IGF受容体、IRS2などのシグナル分子の発現が大きく低下しました。
本研究は、Wnt受容体を中心とする転写調節の分子基盤の解析、Wntシグナルと時間軸(加齢)という新しいパラダイムの観点から、脂肪細胞におけるWntシグナルとエピゲノム研究の礎ともなりました。 本論文の発表と前後して、Wntシグナルと骨代謝についてはヒトでのLRP5遺伝子病osteoporosis pseudo-glioma syndromeも発見されました。また糖代謝、動脈硬化とWntシグナルについては、ヒトでのリンケージ解析から2009年までに140報以上もの論文がサイエンス誌やネイチャージェネティックス誌などを始めとし報告されています。
Wnt/β-cateninシグナルは、核内受容体COUP-TFIIを介してエピジェネティックにPPARγ遺伝子発現を抑制し、脂肪細胞分化を制御する
- Wnt蛋白による脂肪細胞分化の抑制機構の転写シグナルとエピゲノム解析 -
Okamura M, Kudo H, Wakabayashi K, Tanaka T, Nonaka A, Uchida A, Tsutsumi S, Sakakibara I, Naito M, Osborne TF, Hamakubo T, Ito S, Aburatani H, Yanagisawa M, Kodama T, Sakai J. (2009) COUP-TFII acts downstream of Wnt/β-catenin signal to silence PPARγ gene expression and repress adipogenesis. Proc Natl Acad Sci U S A. 106, 5819-5824.
脂肪細胞は、栄養摂取と栄養消費などの代謝変動に対応し、過剰な栄養分を脂肪としてエネルギーを貯蔵する重要な組織です。エネルギーバランスが崩れ、脂肪組織への過度な脂肪蓄積は肥満や生活習慣病を引き起こします。 脂肪細胞分化の過程においてWntシグナルは強力な分化抑制シグナルであることが知られています。Wntは細胞外分泌蛋白で脂肪分化を抑制する一方、骨分化では促進的な役割を担います。実際、Wnt受容体であるLRP5の遺伝子異常による機能低下は個体レベルで骨密度の低下を引き起こします(Fujino, T, Sakai J et al, PNAS 2003, 100, 229-234.)。しかし、Wntが脂肪細胞分化を抑制する分子メカニズムはこれまで明らかではありませんでした。
私たちは、細胞外分泌蛋白であるWntが脂肪細胞分化を抑制するメカニズムを、トランスクリプトーム解析とChIP on Chipを融合させたシステム生物学的な方法により解析を試みました。脂肪細胞分化のモデル細胞である3T3L1細胞でのトランスクリプトーム解析からWntは核内受容体の一つであるCOUP-TFIIを強く誘導すること、そしてこの細胞でのβカテニンのChIP on ChipからCOUP-TFIIがWnt/βカテニンの直接の標的遺伝子であることを、まず明らかにしました。βカテニンは、WntがLRP5に結合すると細胞質にある核蛋白TCF7L2と核内で複合体を形成して転写活性化能を示す蛋白です。COUP-TFIIの3T3L1への強制発現は脂肪細胞の分化を抑制し、逆にRNA干渉によりCOUP-TFIIの発現を低下させると脂肪細胞に分化しやすくなりました。
以上より、細胞外分泌蛋白であるWntが脂肪細胞の分化を抑制するメカニズムとして、核内受容体COUP-TFIIを介し、脂肪細胞のマスターレギュレーターであるPPARγ遺伝子発現をヒストンの脱アセチル化を介して抑制する一連のメカニズムを明らかにしました。
核内受容体PPARδの生活習慣病治療薬への適応
- 運動しなくても余分な脂肪を減らす薬-
Tanaka T, Yamamoto J, Iwasaki S, Asaba H, Hamura H, Ikeda Y, Watanabe M, Magoori K, Ioka RX, Tachibana K, Watanabe Y, Uchiyama Y, Sumi K, Iguchi H, Ito S, Doi T, Hamakubo T, Naito M, Auwerx J, Yanagisawa M, Kodama T, Sakai J. (2003) Activation of peroxisome proliferator-activated receptor delta induces fatty acid beta-oxidation in skeletal muscle and attenuates metabolic syndrome. Proc Natl Acad Sci U S A, 100, 15924-15929.
生活習慣病は肥満、高血圧、高脂血症、糖尿病、加齢などを伴いメタボリックシンドロームとも呼ばれ、心筋梗塞、脳梗塞など血管病変を主とした病気の主原因であります。
核内受容体の一つPeroxisome Proliferator-Activated Receptor δ のアゴニストによる活性化により、骨格筋での脂肪のβ酸化が亢進し、高脂肪食による肥満・糖代謝異常を劇的に改善することを示し、PPARδが治療薬の標的となることを示しました。
網羅的遺伝子発現解析からPPARδの活性化によって、脂肪酸トランスファー、脂肪酸酸化、エネルギーを熱として放出する蛋白(UCP)などが骨格筋細胞で誘導されることが明らかになりました。
このことから核内受容体PPARδを刺激することで、たとえ飽食下であっても脂肪蓄積ではなく燃焼・消費するための遺伝子発現が誘導され、細胞に蓄積された脂肪が消費されることが推定されました。 そこでPPARδの作動薬を高脂肪食下の動物に投与したところ、白色脂肪細胞を中心に貯蔵されている中性脂肪は分解され、劇的に肥満・耐糖能・インスリン感受性を改善がみとめられました。 私たちはPPARδの生活習慣病治療薬への適応を提示いたしました。
脂肪細胞のマスターレギュレーターPPARγがエピゲノム修飾酵素の遺伝子発現を制御することを介して脂肪細胞への分化を制御する
Wakabayashi K, Okamura M, Tsutsumi S, Tanaka T, Hamakubo T, Kodama T, Aburatani H, Sakai J: PPARγ/RXRα Heterodimer Targets Genes of Histone Modification Enzymes Setd8 and Regulates Adipogenesis through a Feed-back Mechanism. Mol. Cell. Biol., 29, 3544-3555.
肥満を始めとする生活習慣病は多遺伝子疾患であり、環境因子との関わりもまた大きな要因です。こと、生活習慣病は環境により体質が変わるという考え方に基づいています。これまでの研究では遺伝子の塩基配列の変異が病気のなりやすさを決定すると考えられて研究がすすめられてきましたが、ゲノム解読からこうした考え方に疑問がうまれてきています。特にエピゲノムという考え方により、栄養が体質を変えるという新たな考え方がもたらされつつあります。
我々ヒトの細胞では、DNAは8分子のヒストンタンパク質にまきついて、ヌクレオソームという構造をつくります。ヒストンはアミノ酸がメチル化されるなどの修飾をうけ、複製の時にこのヒストン修飾も複製されます。ヒストンH3の9番目のアミノ酸リジン(H3K9と略される)がメチル化されるとサイレンシングに働き、ヒストンH4の20番目のリジン(H4K20と略される)のメチル化は、活性化にもサイレンシングにも働きます。 Peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ)は核内受容体型のリガンド応答性の転写因子であり、肥満にともなうインスリン抵抗性の改善薬であるチアゾリジン誘導体(TZD)の分子標的です。核内受容体PPARγの標的遺伝子のゲノムワイド解析(ChIP on Chip解析)から、エピゲノムを制御する標的遺伝子の探索を行いました。その結果、PPARγによってヒストンH3の9番目のリジン(H3K9)のメチル化酵素は転写レベルで負に、ヒストンH4の20番目のリジン(H4K20)のモノメチル化酵素Setd8は正に制御される標的遺伝子であることを見いだしました。 そして、H3K9トリメチル修飾は脂肪細胞分化抑制に、そしてH4K20モノメチル化は分化促進に働くことを明らかにしました。
このようにしてPPARγはこれらヒストン修飾酵素遺伝子の発現を制御し、さらにこれを介して脂肪細胞の分化をエピゲノムの角度から制御する新たな経路があることを報告しました。
脂肪合成を阻害する化合物の作製に成功
(京都大学、ベイラー医科大学、東京大学)
国立大学法人 京都大学(総長 松本 紘)、米ベイラー医科大学(総長 ウィリアム T. バトラー)、国立大学法人 東京大学(総長 濱田 純一)は、脂肪の生合成を阻害する化合物を発見し、その作用メカニズムをつきとめました。この結果は、糖尿病や脂肪肝などの代謝疾患の研究や治療に役立つと期待されます。
京都大学 物質−細胞統合システム拠点(iCeMS=アイセムス)の上杉志成教授、米ベイラー医科大学のサリ・ワキル教授、東京大学先端科学技術研究センター 代謝医学分野の酒井寿郎教授らの研究グループは、ファトスタチンという有機化合物を発見し、その化合物が細胞内で脂肪の生合成を阻害することをつきとめました。詳細な研究によると、ファトスタチンはSCAPというステロール量を感知するセンサータンパク質に結合し、SREBPという転写因子を阻害します。これによって脂肪の合成に必要な遺伝子が活性化しなくなり、糖から脂肪の合成が抑えられます。 この化合物をマウスに投与したところ、過食による肥満、糖尿、脂肪肝を抑制しました。完全合成化合物で、SREBPを阻害する化合物はファトスタチンが初めてです。この合成有機化合物は、代謝疾患(メタボリックシンドローム)を理解する研究に役立つと考えられます。また、この化合物の類縁体が糖尿病や脂肪肝などの代謝疾患の治療薬として将来利用される可能性もあります。
これらの結果は8月27日付けの米科学誌ケミストリー・アンド・バイオロジーに発表されました。
A small molecule that blocks fat synthesis by inhibiting the activation of SREBP.
Kamisuki S, Mao Q, Abu-Elheiga L, Gu Z, Kugimiya A, Kwon Y, Shinohara T, Kawazoe Y, Sato S, Asakura K, Choo HY, Sakai J, Wakil SJ, Uesugi M. Chem Biol. 2009 Aug 28;16(8):882-92.
[PubMed]
研究成果解説
1.背景
メタボリックシンドロームは、過剰な脂肪や炭水化物の摂取に主に起因します。炭水化物から脂肪酸やコレステロールへの変換には数多くの酵素が関与していますが、これらの酵素の発現レベルを包括的に制御しているのは、SREBP(sterol regulatory element-binding protein)という転写因子です。SREBPは細胞の小胞体の膜に結合した前駆体として合成されます。この前駆体が切断酵素によるプロセシングによって、膜から切り離されることにより、核内の標的遺伝子の転写を活性化することが可能になります(Sakai J et al Cell 1996, Sakai J et al Mol Cell 1998)。
このSREBPのプロセシングは、コレステロールなどのステロールによって厳密に制御されています。ステロールは、小胞体の膜上に存在するSREBPのエスコートタンパク質であるSCAP(SREBP cleavage-activating protein)と結合することによりSREBPのプロセシングを制御しています。 SREBPは脂質代謝の恒常性を維持する上で、極めて重要な転写因子です。 上杉研究室では以前、培養細胞の脂肪油滴の蓄積を阻害する化合物としてファトスタチンという化合物を見出しました。本研究では、ファトスタチンがSREBPの活性プロセスを抑制し、脂肪合成を抑制することを明らかにしました。
2.研究手法
最初にDNAマイクロアレイにより、ファトスタチンが作用する細胞内の経路を特定することにしました。続いて、細胞生物学的手法により、さらに詳細な作用機構を調べました。一方で、ファトスタチンの誘導体を合成し構造活性相関を調べました。そして活性に影響を与えない部位に、蛍光物質やビオチンを導入することにより、ファトスタチンが結合するタンパク質を探すことにしました。また、ファトスタチンの薬理学的な効果を調べるために動物実験を行いました。
3.研究成果
DNAマイクロアレイによる遺伝子発現解析などにより、ファトスタチンはSREBPの経路に作用していることが示唆されました。さらに細胞生物学的解析を行った結果、ファトスタチンはSREBPの活性化プロセスを抑制していることがわかりました。蛍光標識したファトスタチンを用いて細胞内の局在を調べたところ、ファトスタチンは小胞体に局在することが明らかになりました。また、ビオチン化ファトスタチンを用いて結合実験を行ったところ、ファトスタチンはSCAPに結合することが示唆されました。以上の結果から、ファトスタチンは小胞体上でSCAPに結合し、SREBPの活性化プロセスを抑制することが示されました。
さらに、肥満のモデルであるob/obマウスを用いて動物実験を行いました。ob/obマウスの異常な体重増加は、ファトスタチン処理によって抑制されました。ob/obマウスではインスリン抵抗性による高血糖や脂肪肝などが見られましたが、これらもファトスタチン処理により改善されました。また、ファトスタチンで処理したマウスの肝臓抽出物中の脂肪酸合成酵素、アセチルCoAカルボキシラーゼなどの脂肪合成に関わるタンパク質は減少していました。つまり、ファトスタチンは動物の肝臓中のSREBPの活性化を阻害し、脂肪合成を抑制していると考えられます。
4.今後の期待
生理活性小分子は、代謝経路などの複雑な細胞内プロセスを解明する道具として利用されてきました。SREBPの機能を調節する小分子は代謝性疾患の治療に役立つ可能性があり、これらの疾病をさらに理解する上での道具となるかもしれません。細胞および動物実験の結果から、ファトスタチンはステロールセンサーであるSCAPに結合し、転写因子SREBPの活性化プロセスを抑制することにより、脂肪合成系の遺伝子の発現を抑制していることが示唆されました。我々が知る限り、ファトスタチンは細胞、マウスの肝臓両方でSREBPの活性化を阻害する、最初の非ステロール合成分子です。
ファトスタチンはメタボリックシンドロームの薬物療法のリード候補であり、ヒトを含む動物の脂質代謝の役割を理解するための道具となる可能性があります。
研究成果のポイント
- 細胞内での脂肪合成を阻害する化合物を発見
- その化合物の作用メカニズムを解明
- 肪合成の阻害剤自体はスタチンなどの酵素阻害剤などこれまで知られているが、今回の化合物はステロール量を感知するセンサータンパク質に働き、包括的に脂肪合成を阻害する
- ネズミに投与したところ、過食による糖尿、肥満、脂肪肝を抑えた
- 代謝疾患の研究や創薬研究に役立つと期待される
甲状腺プロホルモン活性化酵素Iodothyronine Deiodinase 1 (Dio1)遺伝子の転写制御機構の解明
− HNF4α、KLF, GATA4はDio1遺伝子プロモーターを相乗的活性化する (Mol. Cell Biol., MCB.02154-02107) −
甲状腺ホルモンはエネルギー代謝やコレステロール代謝などに重要な役割を担います。甲状腺ホルモンは甲状腺からプロホルモンT4(thyroxin)として分泌され、肝臓や筋肉などで生理的に強い活性を示すT3(3,5,3'-triiodothyronine)へと変換されます。 この変換酵素はiodtyronin deiodinaseとよばれ、局在と調節の異なる2つの酵素(Dio1とDio2)がこれを担います。
Dio1は肝臓に高く発現し、T4をT3に変換する主要な変換酵素です。私たちは肝臓に主要な発現を示す核内受容体HNF4αの肝臓特異的な欠損マウス(H4KivKO)の解析から、肝臓でのDio1のmRNAがほぼ消失していることを見いだしました。 これに伴いDio1酵素活性はH4KivKOマウスにて90%以上の減少が認められました。血中T4とrT3レベルはコントロールFloxマウスと比べ有意な上昇、TSHレベルは減少が認められ、T3レベルには変化が認められませんでした。 T3はDio1やDio2の遺伝子欠損マウスでも変化しないことが既に報告されており、T3を維持する強力なバックアップ機構の存在が示唆されました。マウスDio1のプロモータ解析から、HNF4αresponsive element(HNF4αRE)を見いだし、ここにHNF4αが結合し転写制御を行うことを明らかとしました。
さらに、我々はKruppel-like transcription factor 9 (KLF9)は甲状腺ホルモンで5倍にその転写が上昇することを見いだし、HNF4αREの上流と下流の2つのCACCCボックスを介してDio1プロモータを活性化すること、さらにGATA4とHNF4αが転写複合体を形成し、これを相乗的に活性化すること、クロマチン免疫降法によって内因性のGATA4とKLF9がDio1プロモータに結合することを明らかとしました。 HNF4αとGATA4、KLF9とHNF4αの結合ドメインも共免疫沈降法、GST pull down法、mammalian two hybridにより明らかとした。
以上より、HNF4αがGATA4とそして甲状腺ホルモンによって転写制御されるKLF9によって甲状腺のホメオスタシスを担う新たな転写ネットワークを明らかとしました。
Ohguchi H, Tanaka T, Uchida A, Magoori K, Kudo H, Kim I, Daigo K, Sakakibara I, Okamura M, Harigae H, Sasaki T, Osborne TF, Gonzalez FJ, Hamakubo T, Kodama T, Sakai J.
Hepatocyte Nuclear Factor 4{alpha} contributes to thyroid hormone homeostasis by cooperatively regulating the type1 Iodothyronine Deiodinase gene with GATA4 and Kruppel-like transcription factor 9.
Mol Cell Biol. 2008 Apr 21 [Epub ahead of print]
[PubMed]
Hsp/c70とCHIP E3リガーゼの協調的な相互作用が小胞体タンパク質の品質管理を決定する
細胞内には約数千種類ものタンパク質が発現しており、個々のタンパク質はタンパク質-タンパク質相互作用を介して多彩な機能を発揮することで細胞の生命活動を支えています。
ここに3種類のタンパク質X, Y, Zがあったとします。タンパク質Xはタンパク質Yと直接結合し、タンパク質Yはタンパク質Zと直接結合します。タンパク質Xはタンパク質Zと直接結合できませんが、タンパク質Xはタンパク質Zと結合しているタンパク質Y(タンパク質Y-Z複合体)と結合することでタンパク質Zと相互作用することができます。ではタンパク質Xとタンパク質Y-Z複合体の結合はどのように制御されているのでしょう?
では実際にX = CHIP, Y = Hsp70, Z = CFTRとします。ユビキチンE3リガーゼCHIPはテトラトリコペプチドリピート (TPR) ドメインを介して分子シャペロンHsp70 のC末端ドメインと結合します。Hsp70は基質結合ドメインを介して変性タンパク質であるCFTR(嚢胞性線維症の原因遺伝子産物)と結合します。Hsp70とCFTRの結合の強さはHsp70のATPaseドメインに結合するヌクレオチドに依存します (Mol. Biol. Cell, 2011)。CHIPはCFTRと直接結合しませんが、CFTRと結合しているHsp70 (Hsp70-CFTR複合体) と結合することでCFTRと相互作用します。CFTRと相互作用したCHIPはU-boxを介してCFTRのユビキチン化を行い、分解を促進します。
この論文では野生型とU-boxに変異を入れたCHIPを用い、CFTRと結合していないHsp70ならびにHsp70-CFTR複合体との結合をin vitroで詳細に解析しました。CHIPのU-box変異はATP存在下においてHsp70との結合を促進し、ADP存在下においてHsp70との結合を強く促進しました。またCHIPのU-box変異はCFTRと結合していないHsp70との結合を促進し、Hsp70-CFTR複合体との結合を強く促進しました。従来CHIPはTPRドメインを介してHsp70のC末端ドメインと結合すると単純に考えられていましたが、CHIPのTPRドメインとU-boxドメイン、Hsp70のATPaseドメイン、基質結合ドメインとC末端ドメインのアロステリックな相互作用が CHIPとHsp70の結合に重要であることが明らかになりました。将来CHIP-Hsp70相互作用を阻害する化合物が見つかれば、嚢胞性線維症において変異型CFTRの分解を抑えることが可能になるかもしれません。
Matsumura Y, Sakai J, Skach WR.Endoplasmic reticulum protein quality control is determined by cooperative interactions between
Hsp/c70 and the CHIP E3 ligase
J Biol Chem. 2013 Aug 30. [Epub ahead of print] [DOI] [PubMed]FBXL10は新規なポリコーム複合体を形成し脂肪細胞の分化を制御する
脂肪細胞がどのように分化しているかの機構を知ることは、肥満の進行やメタボリック症候群といった生活習慣病を理解する上で重要です。本研究では3T3-L1脂肪前駆細胞を用いて脂肪細胞の分化機構を検討し、脂肪細胞分化を抑制する新規の機構を解明しました。
脂肪前駆細胞は細胞同士の接触によって増殖が停止したのち分化誘導剤で処理すると、およそ24時間後と48時間後の2回の細胞周期からなる一過性増殖期(クローナルエクスパンジョン期)を経て8日間で脂肪細胞に分化します。この時、複数の転写調節因子が連続的もしくは互いに遺伝子発現を制御するカスケードが存在し、その中でも核内受容体PPARγはマスター制御因子として働くことが知られています。
最近、ゲノム配列によらない遺伝子の発現制御機構であるエピゲノム制御機構が生活習慣病の発症や細胞分化との関わりで注目されていますが、私たちはエピゲノム因子の一つであるFBXL10(別名KDM2B、JHDM1B)が脂肪細胞分化過程において発現が一過性に上昇することを見出しました。FBXL10の発現は高脂肪食負荷によって肥満したマウスの白色脂肪において約20倍に上昇したことから、FBXL10が脂肪細胞分化や肥満に関係していると考えられました。そのため、脂肪前駆細胞にFBXL10を強制発現したところ、脂肪細胞への分化が抑制され、この細胞ではクローナルエクスパンジョン期における2回目の細胞周期が停止していることが明らかになりました。この分化抑制はFBXL10タンパクのJmjCドメインを必要とせず、F-BoxドメインとLRRドメインを必要としました。F-BoxドメインとLRRドメインを介したタンパク相互作用に注目してショットガンプロテオミクス解析法をおこないFBXL10に結合するタンパク質を検討したところ、BCOR、RING1B、SKP1、PCGF1等が見出されました。このタンパク複合体はポリコーム抑制複合体(PRC1)として、クロマチンコンパクションやヒストンのユビキチン化修飾に関わることが最近報告されています。siRNAを用いてRING1BやSKP1をノックダウンするとFBXL10による脂肪細胞分化抑制や細胞周期の停止が解除されたため、このタンパク複合体は機能的な複合体であることが明らかになりました。一方、CUL1はF-Boxドメインを持つタンパクとSKP1に関連が深く、ポリユビキチン化によるタンパク分解に重要なタンパクですが、FBXL110による脂肪細胞分化抑制には影響しませんでした。FBXL10を含むPRC1複合体が標的とする遺伝子を決定するため分化誘導後48時間後の細胞を用いて遺伝子発現解析とChIPシークエンス解析とを行ったところ、細胞周期関連遺伝子(Cdk1, Uhrf1)やPPARγ遺伝子の遺伝子発現がFBXL10の強制発現によって抑制されることが明らかになり、RING1BがFBXL10によってこれらの遺伝子領域に誘導されることが示されました。以上の結果から、FBXL10がPRC1複合体を形成して標的遺伝子の発現を制御することで脂肪細胞分化を抑制するという機構が示されました。生理的にはFBXL10の発現は脂肪細胞分化過程において一過性に上昇するとともに、肥満マウスの白色脂肪において高発現します。この意義として、FBXL10が多能性未分化細胞から脂肪細胞への分化制御に関わることが示唆されます。
Inagaki T1,2, Iwasaki S1, Matsumura Y, Kawamura T, Tanaka T, Abe Y, Yamasaki A, Tsurutani Y, Yoshida A, Chikaoka Y, Nakamura K, Magoori K, Nakaki R, Osborne TF, Fukami K, Aburatani H, Kodama T, Sakai J2 (1 equal contribution, 2corresponding authors)
The FBXL10/KDM2B Scaffolding Protein Associates with Novel Polycomb Repressive Complex-1 to Regulate Adipogenesis
J Biol Chem. First Published on December 626922, 622014, doi:626910.621074/jbc.M626114.626929